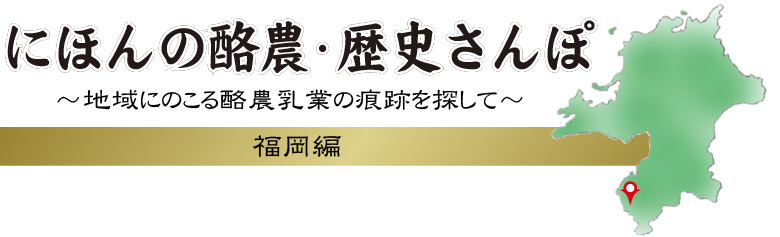
第5回 古い牛乳ビンに見る「牛乳と鉄道」の関係~その1
福岡県内では、小郡市にある九州歴史資料館、築上郡築上町にある旧藏内邸、直方市にある直方市教育委員会の3箇所に、古い牛乳ビンが大切に保管されています。それぞれが「ほぉ~」って感心してしまう特徴的なものですが、それらの牛乳ビンを見ると「牛乳と鉄道」の関係が浮かび上がってきます。
今回は、県内で保管されている古い牛乳びんを紹介しながら、「牛乳と鉄道」の関わりを探ります。
今回は、県内で保管されている古い牛乳びんを紹介しながら、「牛乳と鉄道」の関わりを探ります。
九州歴史資料館所蔵の牛乳ビン
福岡県小郡市にある九州歴史資料館。大陸と向き合い古くから対外交流の窓口としての役割を果たしてきた九州の歴史とその特質を明らかにするため、多角的な調査や研究を行う福岡県立の歴史系博物館です。
-

福岡県小郡市にある九州歴史資料館(九州歴史資料館提供)
この資料館で所蔵しているのが、福岡県福岡市博多区の吉塚本町遺跡から出土した牛乳ビンです。「牛乳ビンが遺跡から出土?そんな大げさな」って思わず笑ってしまいそうになりますが、この牛乳ビン、福岡県教育委員会が1992(平成4)年に発行した「福岡県文化財調査報告書第97集『吉塚本町遺跡』」に掲載されているれっきとした文化財なのです。
吉塚本町遺跡は、博多駅の北隣りにある鹿児島本線吉塚駅構内だった場所で、1965(昭和40)年ごろまでは操車場があり、1975(昭和50)年頃には国鉄博多保線区妙見宿舎があったところ。そこに福岡県中小企業振興センターを建設する話が持ち上がり、工事を行う前、1991(平成3)年9~12月に発掘調査が行われました。基本的には奈良時代を中心とする集落遺跡で、建物跡や土師器、須恵器などが出土していますが、妙見宿舎跡から、駅弁容器や駅弁用のお茶セット、酒ビン、ビールビン、サイダービン、ラムネビン、牛乳ビンなど、主に明治・大正から昭和期前半の生活用具が多量に発見されました。発掘された文化財は、「福岡県文化財調査報告書第97集『吉塚本町遺跡』」に図入りで詳しく掲載されています。
吉塚本町遺跡は、博多駅の北隣りにある鹿児島本線吉塚駅構内だった場所で、1965(昭和40)年ごろまでは操車場があり、1975(昭和50)年頃には国鉄博多保線区妙見宿舎があったところ。そこに福岡県中小企業振興センターを建設する話が持ち上がり、工事を行う前、1991(平成3)年9~12月に発掘調査が行われました。基本的には奈良時代を中心とする集落遺跡で、建物跡や土師器、須恵器などが出土していますが、妙見宿舎跡から、駅弁容器や駅弁用のお茶セット、酒ビン、ビールビン、サイダービン、ラムネビン、牛乳ビンなど、主に明治・大正から昭和期前半の生活用具が多量に発見されました。発掘された文化財は、「福岡県文化財調査報告書第97集『吉塚本町遺跡』」に図入りで詳しく掲載されています。
-

福岡県文化財調査報告書第97集「吉塚本町遺跡」 -

現在の吉塚駅
-

1955(昭和30)年頃の吉塚操車場と発掘調査地区(福岡県文化財調査報告書第97集「吉塚本町遺跡」77頁 第57図)
牛乳ビンについては、「福岡県文化財調査報告書第97集『吉塚本町遺跡』」の82頁第62図「瓶①」、85頁表4に、発掘された牛乳ビン10本の形状、凹凸で浮き上がらせた文字などが詳しく紹介されています。
牛乳びんは、細口で、コルクまたはネジ式のガラス栓で封をしていたようです。広口で、紙またはポリエチレンでフタをしている今の牛乳ビンとは大きく姿が異なります。今の牛乳ビンはビンの表面に商品名やイラストなどをインクで印刷していますが、この時代はそのような技術がなかったのか、ガラスを盛り上げる「陽刻」(エンボス加工)で文字や模様を描いています。また、容量は、0.8合から1.5合とさまざま。表4の1番、2番に「一合五勺入(270ml)」と表示されているのに対し、容量が290mlと多めなのは、生乳をビンに入れてから蒸気殺菌する際に膨張する分を考慮した、当時の製造方法によるものと思われます。
牛乳びんは、細口で、コルクまたはネジ式のガラス栓で封をしていたようです。広口で、紙またはポリエチレンでフタをしている今の牛乳ビンとは大きく姿が異なります。今の牛乳ビンはビンの表面に商品名やイラストなどをインクで印刷していますが、この時代はそのような技術がなかったのか、ガラスを盛り上げる「陽刻」(エンボス加工)で文字や模様を描いています。また、容量は、0.8合から1.5合とさまざま。表4の1番、2番に「一合五勺入(270ml)」と表示されているのに対し、容量が290mlと多めなのは、生乳をビンに入れてから蒸気殺菌する際に膨張する分を考慮した、当時の製造方法によるものと思われます。
-

(福岡県文化財調査報告書第97集「吉塚本町遺跡」82頁 第62図) -

九州歴史資料館が所蔵している古い牛乳ビン
-

発掘された牛乳ビンの詳細(福岡県文化財調査報告書第97集「吉塚本町遺跡」85頁 表4の一部)
ここで気が付くのは駅名が刻まれた牛乳ビンが多いことです。「トス驛」(佐賀県鳥栖市)、「小倉驛」(福岡県北九州市)、「折尾駅」(福岡県北九州市)が各1本に、「博多驛」福岡県福岡市)は2本、10本のうちの半分は駅名が陽刻されています。これは、それぞれの駅でその駅名の付いた牛乳が販売されていたことを示すものです。昔はコンビニもなく、列車の旅は時間がかかります。そのため、駅で駅弁などとともにビン牛乳が販売されていたようです。
-

小倉驛、折尾駅、博多驛の陽刻がある牛乳ビン(九州歴史資料館所蔵)
また、「村田」「楠田」「宮川」「〇〇牧場」「〇〇牛乳株式会社」といった生産者名または販売者名が陽刻されている牛乳ビンもあります。福岡県酪農業協同組合連合会が1976(昭和51)年に発行した『福岡県酪農史』には、八幡市通町(現・北九州市)には1897(明治30)年ごろに村田種吉が設立した村田牧場が、吉塚駅に近い福岡市千代町(現 福岡市博多区千代)に1902(明治35)年に阿部博安が設立した阿部牧場があったとの記載があり、これが「瓶一覧表」2番の「村田」、8番の「阿部牧場」でしょう。
蒸気機関車の汽笛を聞きながら、乗客は列車内で駅弁を食べ、お茶や牛乳などを飲みました。いまでは信じられないでしょうけど、昔はその容器を座席の下に置いたまま下車。博多駅に到着した列車は吉塚駅の操車場に回送、車内清掃で出た駅弁の容器や様々なビン類は次々とゴミ穴に捨てられ、平成になってから掘り出されたのです。
東京は秋葉原駅のホームにある「ミルクスタンド酪」など、現在の駅売りのビン牛乳は、その場で牛乳を飲み干し、ビンを返却するのがルール。これに対し、吉塚本町遺跡からさまざまな駅名の牛乳ビンが出土したということは、昔はその場で飲み干すだけでなく、昔はその場で飲み干すだけでなく、列車内に持ち込むお客さんが相当数いたということですね。
<九州歴史資料館>
住所/福岡県小郡市三沢5208-3
定休日/月曜日(ただし祝日・振替休日の場合はその翌日)
年末年始(12月28日~1月4日)
開館時間/午前9時30分~午後4時30分(入館は午後4時まで)
電話/0942-75-9575
観覧料/第1、3展示室は有料、その他は無料
公式サイト https://kyureki.jp/
蒸気機関車の汽笛を聞きながら、乗客は列車内で駅弁を食べ、お茶や牛乳などを飲みました。いまでは信じられないでしょうけど、昔はその容器を座席の下に置いたまま下車。博多駅に到着した列車は吉塚駅の操車場に回送、車内清掃で出た駅弁の容器や様々なビン類は次々とゴミ穴に捨てられ、平成になってから掘り出されたのです。
東京は秋葉原駅のホームにある「ミルクスタンド酪」など、現在の駅売りのビン牛乳は、その場で牛乳を飲み干し、ビンを返却するのがルール。これに対し、吉塚本町遺跡からさまざまな駅名の牛乳ビンが出土したということは、昔はその場で飲み干すだけでなく、昔はその場で飲み干すだけでなく、列車内に持ち込むお客さんが相当数いたということですね。
<九州歴史資料館>
住所/福岡県小郡市三沢5208-3
定休日/月曜日(ただし祝日・振替休日の場合はその翌日)
年末年始(12月28日~1月4日)
開館時間/午前9時30分~午後4時30分(入館は午後4時まで)
電話/0942-75-9575
観覧料/第1、3展示室は有料、その他は無料
公式サイト https://kyureki.jp/
旧藏内邸所蔵の牛乳ビン
福岡県築上郡築上町にある旧藏内邸は、明治時代から昭和前期まで福岡県筑豊地方を中心に炭鉱を経営し、また大分県などで錫や金の鉱山も経営した藏内家三代の本家住宅です。文化財保護法で認定されている名勝のうち、国が認定を行った全国に408件ある国指定名勝の一つで、公開されています。廊下まで畳敷だし、建物は細部まで作り込まれているし、きれいなお庭を見ながら、煎茶と銘菓寒菊をいただけるし、なかなかいいところです。
-

旧藏内邸の邸宅と庭園(上)、見学時に邸宅内で煎茶と地元の銘菓が味わえる(右下)、弓型天井の廊下(左下)
こちらの展示室で見ることができるのが2本の古い牛乳ビン。これらは旧藏内邸の調査の際に床下から出てきたものだそうです。どちらも、いまの牛乳ビンとは形が異なり、すっきりした細い形状です。それぞれ「辻畑牧畜場」「姫路驛まねき」の陽刻があります。
まずは「辻畑牧畜場」の牛乳ビン。牧場名のほかに「PURE MILK 全乳」「正味量一合入」と刻まれています。こちらを管理している築上町教育委員会の方によると、辻畑姓は築上町にあるので、地元の牧場のものではないかとのことでした。
まずは「辻畑牧畜場」の牛乳ビン。牧場名のほかに「PURE MILK 全乳」「正味量一合入」と刻まれています。こちらを管理している築上町教育委員会の方によると、辻畑姓は築上町にあるので、地元の牧場のものではないかとのことでした。
-

辻畑牧畜場瓶(築上町教育委員会提供)
もう1本が「姫路驛まねき」「消毒済全乳」と陽刻されている牛乳ビン。ここでも駅名が出てきました。しかも九州から遠く離れた兵庫県姫路市の姫路駅です。
-

姫路驛まねき瓶(築上町教育委員会提供)
駅名に続いて書かれている「まねき」を調べたところ、1889(明治22)年に姫路駅構内で弁当、茶の販売を開始し、いまでも駅弁屋、駅そば店を運営している「まねき食品株式会社」のことでした。同社OBの方にお話を伺ったところ、同社の社史に、1930(昭和5)年から牛乳を販売していた旨が掲載されているとのことですので、間違いありません。旧藏内邸で展示されている「姫路驛まねき」の牛乳ビンは、当時、藏内家の当主だった次郎兵衛が、出張がえりに姫路駅の「まねき」のお店で駅弁とともに買い求めたものでしょう。
<旧蔵内邸>
住所/福岡県築上郡築上町大字上深野396
定休日/水曜日(祝日の場合は開館)
年末年始(12月28日~1月4日)
開館時間/午前9時30分~午後4時30分(入場は午後4時まで)
電話/0930-52-2530
入場料/あり
公式サイト https://www.chikujo-rekishi.jp/guide/kyukurauchitei/
<旧蔵内邸>
住所/福岡県築上郡築上町大字上深野396
定休日/水曜日(祝日の場合は開館)
年末年始(12月28日~1月4日)
開館時間/午前9時30分~午後4時30分(入場は午後4時まで)
電話/0930-52-2530
入場料/あり
公式サイト https://www.chikujo-rekishi.jp/guide/kyukurauchitei/
直方市教育委員会所蔵の牛乳ビン
次にご紹介するのが、直方市教育委員会が所蔵している牛乳ビンです。こちらは、直方市勤労者総合福祉センターおよび直方市立図書館の建設に先だって発掘調査が行われた中原田遺跡で出土し、調査結果は「直方市文化財調査報告書第21集『直方市内遺跡群Ⅰ』」に詳細に掲載されています。同遺跡は、直方駅北北西にあり、鉄道建設に伴い付け替えられた山部川の旧流路だったところです。ここから発掘された昭和10年代の時代相を示す陶磁器やガラス製品、鉄道に関する遺物のなかに、牛乳ビンがあったというわけなのです。
-

直方市役所 -

駅前に大関魁皇の銅像が立つ直方駅
-

中原田遺跡周辺地形図。図のまんなかやや上方の黒い長方形が発掘地点(直方市文化財調査報告書第21集「直方市内遺跡群Ⅰ」54頁Fig95) -

出土遺物実測図C(直方市文化財調査報告書第21集「直方市内遺跡群Ⅰ」60頁「Fig105」抜粋)
この牛乳ビンを知ったのは、九州歴史資料館で牛乳ビンを見せていただいたときのこと。どうしても気になり、直方市教育委員会を訪ね、その実物を見せていただきました。長いあいだ地面の下にあったので、表面が銀化して虹色に光っています。けっこう軽めなビンには「消毒全乳」「金拾銭」「直方駅末永牧場」「容器門鉄局認可」「0.一八竕」と刻んでありました。「竕」はデシリットル(0.1L=100ml)のことなので、180ml入りで1本10銭です。
-

直方市教育委員会所蔵の牛乳ビン
ここで気になるのは「容器門鉄局認可」という文字です。「直方市文化財調査報告書第21集『直方市内遺跡群Ⅰ』」によると、「折尾のかしわめし」で有名な株式会社東筑軒(当時は筑紫軒)が、1930(昭和5)年にホーム立ち売りについて鉄道省門司鉄道局の承認を得ているとのこと。つまり「門鉄局認可」とは、末永牧場またはこの牛乳の販売者が、同じように鉄道省門司鉄道局の承認を得たということを示していると思われます。これは見過ごすことができません。
というわけで、「容器門鉄局認可」とは何なのか、もう少し調べてみることにしました。
<直方市教育委員会>
住所/福岡県直方市殿町7-1
電話/0949-25-2000(市役所代表)
公式サイト https://www.city.nogata.fukuoka.jp/
というわけで、「容器門鉄局認可」とは何なのか、もう少し調べてみることにしました。
<直方市教育委員会>
住所/福岡県直方市殿町7-1
電話/0949-25-2000(市役所代表)
公式サイト https://www.city.nogata.fukuoka.jp/
【協 力】
九州歴史資料館 https://kyureki.jp/
旧蔵内邸 https://www.chikujo-rekishi.jp/guide/kyukurauchitei/
築上町教育委員会 https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/li/010/020/080/index.html
まねき食品株式会社 https://www.maneki-co.com/
直方市教育委員会 https://www.city.nogata.fukuoka.jp/
九州鉄道記念館 http://www.k-rhm.jp/
日本経済大学経済学部経済学科 竹川克幸教授
https://www.jue.ac.jp/professor_fukuoka/katsuyuki_takegawa/
久留米市埋蔵文化財センター
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080kankou/2015bunkazai/3020maibuncenter/2007-0711-1250-253.html
九州歴史資料館 https://kyureki.jp/
旧蔵内邸 https://www.chikujo-rekishi.jp/guide/kyukurauchitei/
築上町教育委員会 https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/li/010/020/080/index.html
まねき食品株式会社 https://www.maneki-co.com/
直方市教育委員会 https://www.city.nogata.fukuoka.jp/
九州鉄道記念館 http://www.k-rhm.jp/
日本経済大学経済学部経済学科 竹川克幸教授
https://www.jue.ac.jp/professor_fukuoka/katsuyuki_takegawa/
久留米市埋蔵文化財センター
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080kankou/2015bunkazai/3020maibuncenter/2007-0711-1250-253.html
| 【参考文献】 福岡県教育委員会「福岡県文化財調査報告書第97集 吉塚本町遺跡」1992年 福岡県酪農業協同組合連合会「福岡県酪農史」昭和51年3月 直方市教育委員会「直方市内遺跡群Ⅰ」2000年 一般社団法人日本乳容器・機器協会 牛乳容器の歴史と表示 https://www.namp.or.jp/column4.html 森貴教「牛乳瓶の分類と編年—福岡県を対象として—」 https://researchmap.jp/mori_takanori/published_papers/23442697?lang=ja |
※この記事の文章、写真等は無断転載不可。使用したい場合は(一社)Jミルクを通じ、筆者、所蔵者にお問い合わせください。
執筆者:近藤裕隆
福岡県職員、牛乳パックコレクター、九州鶏すき学会主任研究員、和菓子研究者、普及指導員として酪農家支援を行っていたころ、消費者が求める牛乳の姿を理解するために牛乳パックの収集を開始。平成17年の消費減退と乳価下げを受けて同僚と行う牛乳消費拡大活動のひとつとして、牛乳パックを紹介するブログ「愛しの牛乳パック」を開設しました。以来、「酪農・牛乳にかすればOK」という柔軟な編集方針のもと、酪農・牛乳関連情報の発信を続けています。とはいえ、毎日更新はタイヘンw
ブログ 愛しの牛乳パック http://blog.livedoor.jp/ftmember/
普及畜産チャンネル http://blog.livedoor.jp/fukyuu/
朝倉2号の楽しき日々 https://chspmomo2.yoka-yoka.jp/
福岡県職員、牛乳パックコレクター、九州鶏すき学会主任研究員、和菓子研究者、普及指導員として酪農家支援を行っていたころ、消費者が求める牛乳の姿を理解するために牛乳パックの収集を開始。平成17年の消費減退と乳価下げを受けて同僚と行う牛乳消費拡大活動のひとつとして、牛乳パックを紹介するブログ「愛しの牛乳パック」を開設しました。以来、「酪農・牛乳にかすればOK」という柔軟な編集方針のもと、酪農・牛乳関連情報の発信を続けています。とはいえ、毎日更新はタイヘンw
ブログ 愛しの牛乳パック http://blog.livedoor.jp/ftmember/
普及畜産チャンネル http://blog.livedoor.jp/fukyuu/
朝倉2号の楽しき日々 https://chspmomo2.yoka-yoka.jp/
編集協力:前田浩史
ミルク1万年の会 代表世話人、乳の学術連合・社会文化ネットワーク 幹事 、日本酪農乳業史研究会 常任理事
関連著書 ▶「日本酪農産業史」(単著)[農文協2025年]、「酪農生産の基礎構造」(共著)[農林統計協会1995年]、「近代日本の乳食文化」(共著)[中央法規2019年]、「東京ミルクものがたり」(編著)[農文協2022年]
ミルク1万年の会 代表世話人、乳の学術連合・社会文化ネットワーク 幹事 、日本酪農乳業史研究会 常任理事
関連著書 ▶「日本酪農産業史」(単著)[農文協2025年]、「酪農生産の基礎構造」(共著)[農林統計協会1995年]、「近代日本の乳食文化」(共著)[中央法規2019年]、「東京ミルクものがたり」(編著)[農文協2022年]

